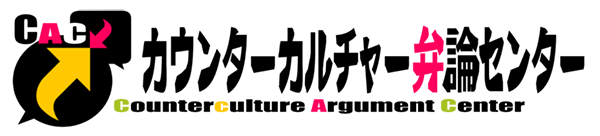今回は『別冊少年マガジン』で2009年10月号(創刊号)より連載が開始し、
11余年の連載を経て、遂に2021年4月9日発売の5月号をもって完結した『進撃の巨人』。
この作品の面白さの秘密を、細かく読み解いて行きたいと思う。
改めて『進撃の巨人』の“面白さ”とは何だったのか?
『進撃の巨人』をこの世に産み落とした諫山創先生という“作者”に焦点をあて、“面白さの本質”に迫っていきたいと思う。
『進撃の巨人』概要
『進撃の巨人』は『別冊少年マガジン』で2009年10月号より連載中の諫山創先生による漫画作品。
小説、テレビアニメ、ゲーム、映画などのメディアミックス展開も盛んで、
単行本の発行部数は、累計1億部を突破している。
あらすじ
巨人がすべてを支配する世界。巨人の餌と化した人類は、巨大な壁を築き、壁外への自由と引き換えに侵略を防いでいた。だが、名ばかりの平和は壁を越える大巨人の出現により崩れ、絶望の闘いが始まってしまう
『進撃の巨人』の成り立ち
ジャンプへの持ち込み
『進撃の巨人』を語る上で、その“誕生秘話”は欠かせない。
『進撃の巨人』の“原型”とも言える最初の“読切版『進撃の巨人』”を
諫山創先生が19歳の時に週刊少年ジャンプ編集部へ“持ち込み”するところから全ては始まる。
2006年、専門学校九州デザイナー学院在学中に読切版『進撃の巨人』を完成させた諫山創先生は、
専門学校の授業の一環として、東京の出版社へ持ち込むという企画があり、
真っ先に幼少の頃より愛読していた週刊少年ジャンプ編集部へ“持ち込み”をする。
その時に窓口担当をしたのは編集者の服部ジャンバティスト哲氏。
結果は“ジャンプの求めるものとは違う”という理由から追い返されてしまう。
因みに諫山創先生は生涯で2度、週刊少年ジャンプ編集部へ“持ち込み”しているが、
もう一方の窓口担当も“服部”と名乗る別人、服部雄二郎氏であった。
その2回の週刊少年ジャンプ編集部への持ち込みを通して、
週刊少年ジャンプの一貫して、
「ジャンプをもってこい」
というスタンスに疑問を抱いた諫山創先生は、“何かに合わせて漫画を描く”という行為は、
漫画を描くのが“作業”になってしまい、“漫画を描く”という、
“本当の意味”が損なわれてしまう。
“作業”でよければネットカフェのバイトでも“やりがい”は見出せる。
諫山創先生は“誰か”から依頼された“作業”がしたい訳ではなく、
“遊びながらお金をもらいたい”から漫画を描くのである。
これは漫画界の“巨人”であり、“ゴールドロジャー(漫画王)”でもある、
尾田栄一郎先生(『ONE PIECE』の作者)の言葉にも通ずるものがある。
「僕は相変わらず働きもせず、漫画ばかり描いてます(by尾田)」と。
マガジンへの持ち込み
諫山創先生の中でひとつの答えが出るのと、時を同じくして、
週刊少年マガジン編集部の門を叩き、“通称バック”こと、
編集者の川窪慎太郎氏と運命的な出会いを果たす。
東京出版社持ち込み企画は、ジャンプ、チャンピオン、マガジンと、すべからく回ったわけだが、
この川窪慎太郎氏と出会うための遠征であったといえる。
人生を左右し、その後の運命を決定付ける出会いは、ある瞬間、歯車がカッチリと噛み合うように不意にやってくる。
人生に一度きりかもしれない、千載一遇のチャンスをつかみとれるかどうかで、凡人と偉人という岐路が決まるのだろう。
そんなこんなで、持ち込んだ読切版『進撃の巨人』のリメイク版(45P)が2006年7月期のMGPで佳作を受賞するが、そこから直ぐに『進撃の巨人』の連載に至ったわけではない。

©諫山創/講談社

©諫山創/講談社
持ち込み時の“読切版『進撃の巨人』”は、
アニメの円盤(DVD&Blu-ray)『進撃の巨人 1 』の、
初回限定特典である“未発表漫画65P「進撃の巨人」0巻”として確認することができるが、
現在の『進撃の巨人』とは根幹に流れる“テーマ”を共通としながら、重要な“設定”のいくつかが大きく異なる。
『進撃の巨人』の“爆発的な推進力”の原動力となった最重要キーワードである、
“壁”と“巨人”との関係性が、この時点での(『進撃の巨人(読切版)』の)設定では“時流とのシンクロ率”も低く、
プロットのテンプレ感も拭えない。
そして当時の週刊少年マガジン編集部も“画力の向上が課題”と評している。
まさに“原石”の状態で、“磨き上げる”のを待つ必要があった。
そんな当時の、まだ原石だった諫山創先生を、担当編集者の川窪慎太郎氏はこう振り返る。
うーん……。主人公の表情を見たときに作家の気持ちが伝わってきて、「ああ、この人は本当にマンガが描きたくてたまらないんだ。表現したいことがあるんだな」と感じたんです。僕は、マンガを描くということは結局、自己を表現することだと思うんですよね。自分の中にある気持ちや考えを、「なんだよくかわからないけど外に出したい」と思ったときにすごい物語が出てくるんじゃないかと。だからどのくらいマンガとして完成しているかっていうことは大した問題じゃなくて。彼の中にそういう気持ちが強くあるっていうのが伝わってきたんです。
川窪慎太郎氏が天才諫山創先生を“発掘”できたのは、漫画の完成度ではなく、
持ち込み作品から、にじみ出ていた“作家の魂(爆発寸前の自己表現)”を見抜いたからであろう。
まだ世に出すには未完成の『進撃の巨人』は諫山創先生の中で数年かけて磨かれていくこととなる。
別冊少年マガジン創刊
時は流れ、2009年9月、新たに創刊予定だった『別冊少年マガジン』の連載枠を巡り、第一回連載コンペが開催されていた。
第一回コンペのテーマは“ダークファンタジー”
『別冊少年マガジン』の連載コンペ向けに何案か既にプロットを切っていた諫山創先生であったが、
そのプロットを見て、面白いとは思いつつも、コンペに回すのに踏み切れずにいた川窪慎太郎氏は“記憶の片隅に”なぜか印象に残っていた、
“読切版『進撃の巨人』”を思い出す。
「連載用に進撃の巨人の“裏設定”的なものは考えてないのか?」
諫山創先生に尋ねると、色々な設定が語られ、
そのどれもがすごく面白かったという。
こうして読切版『進撃の巨人』は連載用に練り直され、連載コンペに挑むこととなる。
連載用に練り直した『進撃の巨人』は見事連載を勝ち取り、
2009年9月9日発売の『別冊少年マガジン』創刊号から連載をスタートさせる。
無名の新人としては異例の“センターカラー”で掲載された。
連載コンペでは第1話と第2話のネームで連載枠が決められたようだが、
連載が決まった後に急遽“5年前のエピソード”を新たに2話分、ネームを描き下ろし、掲載直前で差し替えている。
つまり、連載コンペ用に提出した第1話と第2話は、現在の第3話と第4話に相当する。
ネームバリューのない新人にとっての初連載は、“一話一話”が“生死を分ける”
「ワンショット!ワンキル!」チャンスは1回!
スナイパー精神が欠如している新人漫画家は即廃業の運命を辿る。
連載コンペに提出された幻の第1話と第2話のネーム(現在の第3話と第4話に相当)は
『進撃の巨人 OUTSIDE 攻』で確認することができるが、
新人らしい生き残りをかけたネームは連載コンペ用の方である。
現在の第1話は“長編の冒頭”を強く意識した構成になっており、
『進撃の巨人』という作品の第1話としてはもちろん“正解”である。
とはいえ、無名の新人にとって“次”がある保障はどこにもない。
壮大な物語の冒頭を意識し過ぎた第1話では最悪、
“打ち切り”という運命も可能性としては十分ありえた。
これは、ネームバリューのある作家なら、多少、冗長な冒頭でも、
ある意味、面白さがネームバリューにより担保されているため、読者も腰を据えて鑑賞できるが、
無名の新人が、同じことをしてしまうと、最悪、面白さを見出す前に読み飛ばされてしまう危険性がある。
そのため、無名の新人、新連載第一話の王道戦略は、読者を飽きさせずに1ページでも多く読んでもらえるように、
物語の“整合性”よりも、派手さや意外性を構成度外視で連発する傾向にある。
そのような、王道戦略から、急遽、壮大な物語の冒頭を意識した構成に切り替えた『進撃の巨人』。
結果的に“打ち切り”は免れ、『進撃の巨人』は“大ヒット”した。
なぜか?
それは諫山創先生の考える“面白さの本質”に答えがある。
『進撃の巨人』“面白さの本質”に迫る
『進撃の巨人』の面白さを語る上で、重要なキーワードとして、
- 巨人
- 壁
- 立体機動
がある。
これらが、複雑に化学反応を起こして、読切版にはなかった“時流とのシンクロ”を、連載版では果たした。
「巨人」と「壁」と「立体機動」

©Mainichi Broadcasting System, Inc.
まず、『進撃の巨人』の“世界観”を決定付ける要素に、“壁”の存在がある。
これは、諫山創先生が幼少の頃より生活していた、大分県日田市(旧大山町)の“原風景”がモチーフのひとつになっている。
360°見渡す限り山々に囲われた“閉塞感”は、山育ちの田舎出身者“あるある(ネタ)”ではなかろうか?
読切版の“壁”は、“大木”で設定されており、まさに、「(大自然に囲まれた)田舎で、(成功の象徴である)都会を夢見る作者の現状(当時)」と重なる。
連載版では、正真正銘の“壁”となり、『進撃の巨人』を象徴するシンボルのひとつになるのと同時に、様々なメタファーの象徴としても機能した。
普通は99%の確率で漫画家の夢は破れる
諫山創先生は19歳の時、専門学校に進学し、同じように漫画家を目指す同志と出会い、
「こんな地方の専門学校でも、自分よりマンガの巧い奴がたくさんいる」
「全国にはもっとマンガの巧い奴はたくさんいるハズ…」
地元を離れ、現実を思い知った諫山創先生は、20歳で上京した後もずっと、
「30歳くらいまではバイトで生活費を稼ぎながら、マンガを描くも、そのまま鳴かず飛ばずで、いずれは実家に帰る確率が9割以上…」
と、冷静に自己分析していた。
諫山創先生は、19歳でノートパソコンを入手し、“ネットと繋がった”瞬間に人生観が変わったとも語っている。
TVや雑誌では、成功者の体験談しか語られない。
しかし、その裏には数えきれない失敗や挫折があり、むしろそちらの方がありふれている。
ネット上には、漫画家を目指し、夢破れた漫画家志望者たちのリアルな声が、ブログや掲示板に数多、遺されており、
それらが物語るひとつの事実として、
“普通”は、99%の確率で、漫画家になる夢は破れ去る。
「自分だけが“特別”だという保証はどこにもない。」
このような、“漫画家”として成功できるかわからない、漠然とした将来への不安や焦りが、
『進撃の巨人』1巻までのテーマにも如実に投影されている。
ネット環境が急速に発達したゼロ年代以降、誰もが発信側に回れるようになった。
これは、いい意味でも悪い意味でも、すべてを曝け出してしまう世界と直面したともいえる。
今までは成功者の体験談しか表に出てこなかった、
それが、ネットの発達により、その何十倍もの失敗談を表に曝け出したように。
奴隷の幸福か、地獄の自由か
『進撃の巨人』の重要なテーマのひとつに、
「奴隷の幸福か、地獄の自由か」
がある。
家畜のように柵の中に囚われている時、確かに不自由だが、
同時に、一定の安寧も保証されている。
自分の頭で考えなくとも、少なくとも最低限の衣食住は与えられるからだ。
これが“奴隷の幸福”。
一方、柵の外には自由がある。
しかし、自分を襲ってくる外敵や、衣食住を自分の力で手に入れなければならない。
これが“地獄の自由”。
この二つの領域を分断している境界線が“壁”である。
人間の根源的な欲求として、
常に、“奴隷の幸福”と“地獄の自由”を行き来し、ゆらいでいる。
壁内住民と調査兵団、社畜と脱社畜、建前と本音…etc。
壁というモチーフが、時流とシンクロしたのは、必然だったのかもしれない。
そして、このゆらぎは、まぎれもなく、作者である諫山創先生の心理状態ともシンクロしていた。
超大型巨人は“神”

壁と“対”になる存在として、
“巨人”がある。
読切版からも読み取れるように、『進撃の巨人』の初期プロットの構成からも“巨人”がアイデアの起源であり、起点になっているのは間違いない。
壁の方が前述のようにメタファーとしては解釈しやすいが、初期プロットやログラインから逆算すると、壁は“巨人”を効果的に魅せる舞台装置に過ぎず、
“巨人”こそが本作のメインテーマといえる。
この巨人の起用は、業界関係者内では、「ここがあったか!?」「やられた!!」といった声が散見された。
まさに“盲点”ともいえるモチーフで、
元来から日本国内では、『ゴジラ』や『ウルトラマン』などの巨大怪獣系特撮モノや、巨大ロボット系アニメがお家芸的に発達してきた文化があり、
巨大怪獣や巨大ロボットにはそうした文化の影響も手伝い、接触機会も多かったのだが、
何故か、所謂、“巨人”に関しては、日本人には馴染みの薄いモチーフとして、見向きもされてこなかった歴史がある。
しかし、もともと、日本人は、巨大なものへの憧れや、畏敬の念が強く、巨人も当然、例外ではない。
更に、巨人が、他の巨大モノ作品と一線を画す要素に、
見た目は“人間そのもの”だという不気味さがある。
見た目は同じ人間なのに、“巨大”で“何を考えているかわからない”となると、
強烈なまでの“同族嫌悪”が湧きおこる。
“ぜんぜん”違うより、“少し”違う方が、嫌悪感は増幅しやすい。
少ししか違わないのに、意思疎通できないほど不気味なことはないからだ。
実際、この巨人の不気味な設定は、諫山創先生の体験がもとになっている。
読切版の巨人は、“怪獣”や“モンスター色”が強く、
この時点では、連載版のもつ“不気味さ”が存在しなかった。
その後、読切版が新人賞を獲り、授賞式で少年マガジン森田浩章編集長から
「巨人をもっと怖く」との助言を受け、
諫山創先生がネットカフェでアルバイトをしていた時に遭遇した、泥酔客との体験を思い出す。
泥酔し「何を考えているかわからないのに知恵はある」客とのやりとりで感じた、
見た目は同じ人間なのに、“意思疎通”できないことの、言い知れぬ恐怖。
この時の体験をもとに、連載版の巨人は、記号的な“モンスター”ではなく、
その辺にいそうな“普通の人”が、ただただ“巨大”で、
しかも、“何を考えているかわからない”という、
『進撃の巨人』特有の不気味な巨人が誕生した。
これだけでも不気味な巨人が、更に衝撃的なのが、
“人を食う”こと。
その辺にいそうな“おっさん”が裸体のまま走り回り、
人を食う。
しかも、“ベキバキ”と汚らしく食い散らかす。
猛獣や怪獣、モンスターが人を食うのと、
人が人を食うのでは、衝撃の桁が違ってくる。
カニバリズム(共食い)は人類究極の“タブー(禁忌)”だからだ。
このように、『進撃の巨人』の独特の味を形成しているのが、
“無垢の巨人”の存在なのだが、
『進撃の巨人』には、“テーマ”上、欠かすことのできない巨人がいる。
それが、第一話の“見開き”と、単行本の“表紙”を飾る、
“超大型巨人”。
“超大型巨人”は、『進撃の巨人』という作品にとっても、
諫山創先生にとっても、極めて重要な巨人だといえる。
なぜなら、この“超大型巨人”は、この漫画にとって、
“神”だからだ。
巨人は、この世界の絶対的な支配者であり、神と等しき存在。
この神に従わない人たちが、自我に目覚めた主人公や調査兵団であり、
「たとえ地獄でも自由でいたい!」と願う者たちである。
この対立構造を作るためには、どうしても神の存在が必要であり、
その大役を“超大型巨人”が担っている。
諫山創先生も、一度、描き上げた見開き原稿を没にして、描き直したくらい、
超大型巨人の作画には熱量を込めている。
圧倒的、戦力差
巨大な敵との戦いにおいて、人類側の兵器をどう設定するかで、
その作品の方向性が決まる。
少なくとも、『進撃の巨人』の序盤では、巨人との戦力に圧倒的な戦力差が存在した。
その圧倒的“戦力差”こそが、人類側の“絶望”を浮き彫りにし、
先の見えないストーリーテリングに、読者はのめり込んでいった。
読切版では、人類側が、いわゆる少年誌的な超人設定で、身体能力のみで、巨大な敵に立ち向かってしまう。
確かに戦力差はあるのだが、そこに、絶望感は生まれない。
なぜなら、身体能力のみで立ち向かう“少年誌的な文法上”では、
どんなご都合主義でも力技で通せてしまうからである。
連載版では、巨大な敵に対し、“立体機動装置”でやっと射程範囲に届くという、
絶妙な戦力バランスに調整してきた。
“立体機動装置”の仕組み自体は、物理法則を無視した架空の装置だが、
“立体機動装置”が存在するだけで、一気にリアリティ・ラインを確保してくれている。
更に、アニメ化の際、“立体機動装置”のアクションが、話題を呼ぶほど新しい“映像表現”になっており、
この“立体機動装置”の発明で、『進撃の巨人』の世界観を決定付けるパズルのピース、
“巨人” “壁” “立体機動”
すべてが揃った。
面白さの秘密
諫山創先生という“作者”に焦点をあて、
『進撃の巨人』の面白さの秘密を考察してきたわけだが、
諫山創先生自身は、面白さの本質について、こんな言葉を残している。
「僕は究極的に運しかないと思ってるんです。自分が面白いと思っているものが、ほかの人が見て面白い理由は考えてもわからない。」
と。
99%と1%を分かつ境界線である“壁”は、
諫山創先生の見解としては、“運”だという。
これは、どんな些細なことでも、“選ぶ側”の立場を経験したことがあると、なんとなくこの意味がわかる。
「なぜ、神は我を選んだのか?」
筆者はヒョウモントカゲモドキ(Eublepharis macularius)を飼育しているのだが、
このヒョウモントカゲモドキに、生餌であるデュビア(Blaptica dubia)を与えるとき、
数百匹のデュビアの中から“1匹”を選ばなければならない。
この選ばれた“1匹”とその他では、文字通り運命が大きく変わることとなる。
なぜなら選ばれた“1匹”は、ヒョウモントカゲモドキの餌として、その命を終えることになるからだ。
この時、選ばれる“1匹”とその他で、違いがあるとすれば、おそらく“運”しかない。
宝くじに当たる人も、交通事故に遭う人も、漫画家として成功する人も、
その漫画がヒットするかどうかも、
やはり、究極的には“運”なのだろう。
少なくとも、進撃の巨人の面白さの理由は、
作者の“面白い”と、読者の“面白い”が、
偶然“一致”した、“奇跡”だとしか説明がつかない。